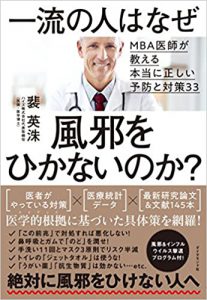病気と歴史 - 胃潰瘍が国民的作家、漱石の『明暗』を未完にさせた(2/3)
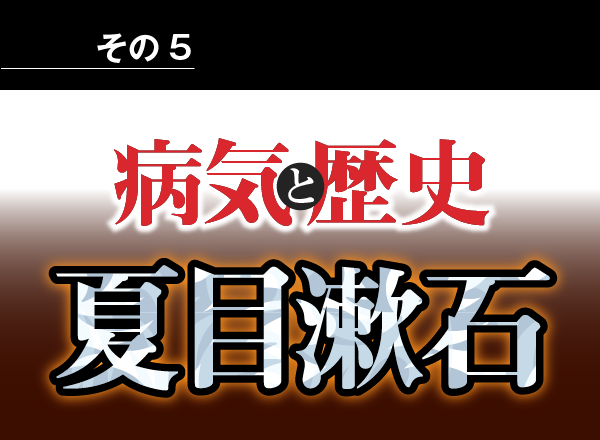
世に修善寺大患と言われる大吐血
当時の胃潰瘍の治療法は、硝酸銀を服用し、コンニャクでおなかを温めるぐらいしかなかった。
漱石は長与胃腸病院を退院した後の明治43年8月6日、弟子の松根東洋城に連れられた伊豆修善寺温泉へ行った。ここで療養中の24日に、漱石は胃潰瘍(消化性胃潰瘍)による大吐血をして生死をさまよった。この出来事は世に修善寺大患といわれ、大事件として扱われたが、そのときの様子を漱石は『思ひ出す事など』に詳しく書いている。他の資料も参考にして、以下、経過を要約して紹介しよう。
漱石は東京を発つ前から喉を痛めていて、修善寺に着いてからもいっこうに良くならなかった。
8月12日に、漱石は黄黒い粘液を一升吐いた。修善寺に来て初めてのことだった。吐き終わった後は多少気分がよくなり、アイスクリームを食べて体の衰弱を防いだ。しかし、すぐに苦しくなり、こらえきれずに吐いた。吐くものはすべて水のような粘液だった。東洋城は、病状の悪化を漱石宅の妻鏡子と朝日新聞社に知らせた。妻が来たし、朝日新聞からは坂元三郎記者(『思い出す事など』では、「雪鳥君」となっている)が駆けつけたし、長与胃腸病院からは森成麟造医師が来た。
8月19日、漱石はまた、血を吐いた。黒ずんだ濃い液が金盥になみなみとたまった。診森成医師は、「今のうちに安静にして早く帰京したほうがよい」と漱石に告げた。嵐山光三郎の『文士温泉放蕩記』(講談社)には、漱石は血を吐きながら、「胃の悪いところを切りとって犬に投げてやりたい」と言ったとある。ちなみに、同書について、同書巻末の池内 紀による解説には、本書について、「実録物で、小説でありフィクションであるが、語られていることのかなりは事実に基づいている。その境界があいまいでボヤけている」と書かれている。
8月24日は長与胃腸病院の杉本副院長が診察に来ることになっていた。漱石はその少し前、妻より吸飲を受け取って、細長い硝子の口から牛乳を1合ほど飲んだ。できるだけ栄養を与えて、体力の回復のほうから、潰瘍の出血を抑えるという療治法を受けつつある際だから、否応なし飲んだ。しかしこれはよくなかったようである。濃い牛乳が胃の中で固まったように妙に落ち着きが悪かった。
漱石を診察した杉本医師は、なにより漱石の気分を落ち着かせることが大事と考えて、「それほど悪くない」と説明した。その報告を受け、付き添っていた坂元記者は、喜びのあまり社(朝日新聞社。漱石は当時、朝日新聞社の社員だった)に向けて、「良い」という電報を打ってしまった。
……ところが、この吉報を逆襲すべく、診察2時間後に、突如として吐血する。800グラムもの大量であった。『思い出す事など』には次のように書かれている。
瀕死の状態、30分の間死んでいた
かく多量の血を一度に吐いた余は、その暮方の光景から、日のない真夜中を通して、明る日の天明に至る有様を巨細もらさず記憶している気でいた。程経て、妻の心覚えにつけた日記を見て、その中に、ノウヒンケツ(狼狽した妻は脳貧血をかくのごとく書いている)を起こし人事不省に陥るとあるのに気がついたとき、余は妻を枕辺に呼んで、当時の模様を委しく聞くことができた。徹頭徹尾明瞭な意識を有して注射を受けたとのみ考えていた余は、実に30分の長い間死んでいたのであった。(『思い出す事など』Vol13)
大吐血した後、食塩水を注射され、容体が少し落ち着いたとき、妻が杉本医師に「これでも元のようになるでしょうか」と聞く声が漱石の耳に入った。が、また気が遠くなったようで、気付けのカンフルを立て続けに注射された。その枕頭で、杉本医師ともう1人の森成医師が次のような会話を交わす。
「弱い」
「ええ」
「駄目だろう」
「子供に会わせたらどうだろう」
「そう」
それが耳に入った漱石は、今まで閉じていた眼を急に開け、そうして大きな声と明瞭な調子で、「私は子供などに会いたくありません」と言った。
一命をとりとめたが、この体験がその後の作品に影響を与えることになった。漱石はその後、毎年のように胃潰瘍のために入院するなか、大正4年(1915)からは朝日新聞に『明暗』の連載が始まった。
その翌年の大正5年5月、具合が悪くなって倒れ、連載は188回で中断した。容態は悪化し、同年12月、漱石はひどく苦しみはじめ、自分の胸をあけて、「早くここへ水をぶっかけてくれ、死ぬと困るから」といった意味のことをいい、看護婦が水を含んで吹きかけると、「ありがとう」といい、その後、意識を失ってしまった。同日死去、49歳だった。
死因は消化性胃潰瘍による出血と考えられているが……
翌日解剖されたが、胃に大きな潰瘍があり、何度も出血を繰り返した痕があった。出血性胃潰瘍が漱石の命取りとなったのだった。漱石はストレスが胃にくるタイプだったようだ。その性格、気質は精神科医の研究対象になり、うつ病気質ともパラノイアとも診断されている。
修善寺大患に話を戻すと、しかし、胃潰瘍が悪化しているとき、つまり炎症が燃えさかっているとき、温泉につかって温めていいものかどうか。温泉に限らず、温めると潰瘍はますます悪化し、炎症は正常な部分へも浸潤していくのではないだろうか。前出の『文士温泉放蕩記 ざぶん』には次のような記述がある。
8月8日は、朝、入浴して部屋に戻ってから胃痙攣が起こった。しばらく蒲団に伏し、昼寝をして、また入浴した。大風呂につかると、湯が腹にしみて、胃腸の罅(ひび)割れがふんわりとつながり、じんとした痛みがやわらぐのであった。湯の香りが鼻をくすぐり、俳句を詠みたい心境になった。しかし、句想を練ろうとしたときに、チクリと胃が痛み、あわてて湯から上がった。
夜になると、また湯につかった。つかりたては、内臓もゆるりと休まるのだが、それもつかの間で、猛烈な痛みに襲われた。胃を素手で摑みとられるような痛みだった。
また、同書には次のような記述もある。
杉本医師は、朝日新聞の坂元記者に「せっかく温泉に来たのだから、どうぞ入浴なさってください」と勧められ、森成医師とともに湯につかった。湯から上がった2人の医師は坂元医師に、
「温泉治療は胃腸に効果的だが、急激に何回もつかりすぎると、逆効果になる。ドイツには、医師が常駐するクアハウスというものがあり、日本にもそういう施設を造るとよい」と講釈をした。
胃潰瘍の原因は、かつては暴飲・暴食や精神的なストレスと考えられてきた。胃酸の分泌が亢進し、胃壁の粘膜が傷つく。漱石も、『思い出す事など』に、「忙殺されて酸が出過ぎる事も、余は親しく経験している」と書いている。 若い頃の漱石は肉が大好きだったらしい。甘いものが大好きだったし、落花生も好きだったようで、落花生を食べて胃潰瘍を悪化させたこともあった。
しかし、ヘリコバクター・ピロリという細菌が発見された今、胃潰瘍の主因はこの細菌と考えられるようになった。この細菌に感染すると、胃の粘膜が弱り、胃壁が自分の胃酸によって傷つくことなどによって潰瘍ができることがわかっている。
ストレスは潰瘍を悪化させる要因と考えられている。かつて日本人はこの細菌を持っている者が多かったことがわかっているが、漱石もこの細菌に感染していたと見られている。ところが、アスピリンが大出血を引き起こしたという説を発表している医師がいる。
(続く)
文:東/茂由 ライター
1949年、山口県生まれ。早稲田大学教育学部卒。現代医学から東洋医学まで幅広い知識と情報力で医療の諸相を追求し、医療・健康誌、ビジネス誌などで精力的に取材・執筆。心と体、ライフスタイルや環境を含めて、健康と生き方をトータルバランスで多面的に捉えるその視点に注目が集まる。